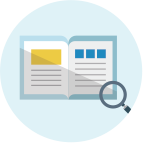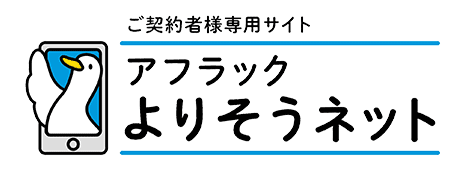新たに保険を
ご検討されている方
お近くのお店で
ご相談をご希望の方
電話以外のお問い合わせ
-
- 生命保険をご検討の方
-
- 保険検討・お申し込みの進め方
- 生命保険商品一覧・シミュレーション
-
- 生命保険の種類から探す
閉じる
-
- ご契約者の方
-
- ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」のご案内
- 各種お手続き
- 給付金・保険金のご請求
-
- 新しく保険を検討したい
-
- 保障を充実させたい
閉じる
-
- 保険について知りたい
-
-
- 保険基本情報
-
- 保険関連情報
閉じる -
-